資格試験は、キャリアアップや転職、独立のチャンスを広げてくれる強力な武器にもなります。
また、何かを学ぼうと思った際に、「何から覚えたらよいかわからない。。。」そんな方は”資格取得”を目標に勉強してみると、体系的な知識を得ることができ、なおかつ資格合格という報酬付きで勉強が出来るのでおすすめです。
しかし、特にビジネスマンの方は仕事と家庭とを両立しながら勉強時間を確保する必要があるため、資格取得する事は簡単な道のりではないと思います。
そこでこの記事では、最短合格を実現するための効率的な勉強の進め方を徹底解説します。
独学や通信講座、予備校など、それぞれに対応した実践的な勉強方法をご紹介していきます!
Step1:スケジュールを立てる
最初にやるべきことは、全体のスケジュール設計です。
行き当たりばったり勉強をするのではなく、効率よく学習を進めることで、最短合格を目指しましょう。
■ 試験日を確認する
まずは受験する資格の試験日を公式サイトで確認しましょう。試験日が決まれば、ゴールが明確になります。
参考までに、主な資格の試験日目安を記載します。
※詳しくは各資格の公式サイトでご確認ください。
| 資格 | 試験日 |
|---|---|
| 日商簿記3級 | 統一試験は6月、11月、2月の年3回 ※CBT方式(Web試験)は定期的(毎週、毎月)に実施 |
| 日商簿記2級 | 統一試験は6月、11月、2月の年3回 ※CBT方式(Web試験)は定期的(毎週、毎月)に実施 |
| 中小企業診断士 | 1次試験:8月初旬 2次試験:10月下旬 |
| ITストラテジスト試験 | 4月中旬 |
| プロジェクトマネージャ試験 | 10月初旬 |
| 宅建士 | 10月中旬 |
| 公認会計士 | 短答式1回:12月初旬ー中旬 短答式2回:5月下旬 論述試験:8月下旬 |
■ 逆算して学習スケジュールを組む
試験日から逆算して、
- いつまでにインプットを終えるか
- いつからアウトプット中心にするか
といった学習フェーズごとの計画を立てます。
Step2:必要な勉強時間を把握する
合格のためには、資格ごとに目安となる勉強時間があります。
例:
- 簿記3級:100〜150時間
- 宅建:300時間前後
- 中小企業診断士:800〜1000時間
この目安をもとに、自分に必要な勉強時間を把握しましょう。
ただし、上記はあくまで目安です。
これまでの社会人経験などで培った経験や知識、物覚えの良さなどで勉強時間は全く異なりますので、「大体このくらい勉強すればよいんだな」ぐらいで把握するのが良いと思います。
試験によって合格ラインが定められていますが、満点を取る必要はなく、試験によっては60点でよい(40点間違えてよい)などもあります。
勉強をはじめる前から噂ベースの勉強時間に臆する必要はありません。
しっかりと計画を立てて取り組んでいきましょう!
Step3:1日あたりの勉強時間を計算する
勉強時間がわかったら、試験日までの日数で割って、1日に必要な学習時間を算出します。
例:300時間必要/残り150日 →「1日2時間」
忙しい方は、
- 平日:1時間
- 土日:3〜4時間
のように曜日ごとの調整も取り入れてください。
Step4:勉強方法を決める(独学・通信講座・予備校のメリット・デメリット)
テキストのみでの独学や通信講座を活用した独学、予備校利用などが考えられますが、それぞれにメリットデメリットがありますので、自分に合った勉強スタイルを選びましょう。
● 独学
- ◎ コストが安い
- △ 教材選びが重要、自己管理力が必要
● 通信講座
- ◎ カリキュラムが整っており効率的
- ◎ 自分のスケジュールに合わせて学習が可能
- ○ 映像講義や質問サポートあり
- △ ややコストがかかる
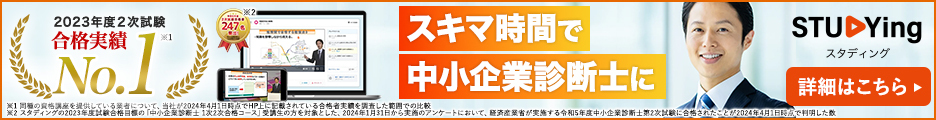
● 資格予備校
- ◎ 講師のライブ授業が受けられる
- ◎ 疑問点などを質問しやすい
- ○ 同じ目標の仲間と刺激し合える
- △ 通学時間と費用が必要
ご自身の予算・ライフスタイル・性格をもとに選択しましょう。
Step5:勉強開始!まずはインプットから
勉強開始後は、まず知識を吸収する「インプット」フェーズからスタートです。
予備校に通われている方は、予備校のカリキュラムに沿って学習しつつ、予習・復習を繰り返す事が良いかと思います。
● 独学の場合
信頼できる参考書を1冊選び、まずは一周しましょう。完璧に理解する必要はなく、全体像の把握が目的です。
● 通信講座の場合
講義動画やテキストを活用して、まずは一通りの知識を入れましょう。
通信講座は、解説付きで学べるのが利点です。
動画の倍速再生や移動時間での音のみでの視聴により時間効率を高めることも可能です。
Step6:アウトプット中心に切り替える
インプットがひと通り終わったら、アウトプット重視に切り替えましょう。
資格取得で最も重要なのはアウトプットだと断言します。
分からなくても早い段階で過去問などを解くこと事がおすすめです。
最初は3割も解くことが出来ないと思いますが、数年分を3周ぐらいすることを目指して解いていきましょう。
少しずつ理解できるようになり、試験前には7-8割解けるようになっていると思います。
● 具体的なアウトプット方法
- 単元ごとの問題集に取り組む
- 過去問を解く
- 模試を受ける
過去問を解く際は、ちゃんと時間を測って解くことをおすすめします。
最初のころは時間をオーバーすると思いますが、時間が過ぎても最後まで解いて、どのくらいの時間がかかるのか、把握してください。
試験直前期には、きちんと時間通りに区切って、どのくらいのスピードで解く必要があるのかなど体に染み込ませていきましょう。
● 間違い直しと復習が最重要
「なぜ間違えたか」を分析し、ノートにまとめたり、弱点を繰り返し復習することで定着が進みます。
Step7:PDCAで学習を回す
合格者の多くが実践しているのが、PDCAサイクルです。
- P(Plan)計画:解く問題・過去問を決める
- D(Do)実行:問題を解く(ちゃんと時間を測って解きましょう)
- C(Check)確認:間違えた問題と正しい解答を確認する(解答に詳細な記載がない、理解できない点など不明点はすぐに調べてノートなどに整理しましょう)
- A(Action)改善:正しい答え、解法を理解し、余裕があればすぐに解きなおしてみましょう。
これを繰り返すことで、自然と知識が身につきます。
Step8:模試や過去問で実力チェック
試験1〜2ヶ月前からは、本番形式の模試や過去問に取り組みましょう。
- 時間配分に慣れる
- 試験の出題傾向を把握する
- 得意・苦手分野を洗い出す
本番を意識したアウトプットは、得点力アップの鍵です。
まとめ:最短合格は「戦略」+「継続力」
資格試験において大切なのは、やみくもに勉強するのではなく、正しい勉強方法で戦略的に、そして継続的に取り組むことです。
成功のポイント
- ゴール(試験日)から逆算して計画を立てる
- 勉強方法は独学・通信・予備校から自分に合ったものを選ぶ
- とりあえずインプットを終わらせる
- 早めにアウトプット(過去問など)を始める
- PDCAを繰り返す
- 模試や時間を測っての過去問で仕上げを行う
最短合格は、毎日の積み重ねの先にあります。ぜひ今日から、一歩を踏み出してみてください!
コロナ禍に会食の機会が減ったことをきっかけに独学で簿記2級に合格。そこから資格試験に目覚め、中小企業診断士、応用情報技術者、プロジェクトマネージャー試験に合格。難関資格合格の経験から最短合格を目指す方向けに資格受験のコツや勉強の進め方、通信講座の選び方をお伝えします。
現在は独立を目指しながら、企業内診断士として中小企業支援中
【保有資格】中小企業診断士、簿記2級、応用情報技術者、プロジェクトマネージャ試験など
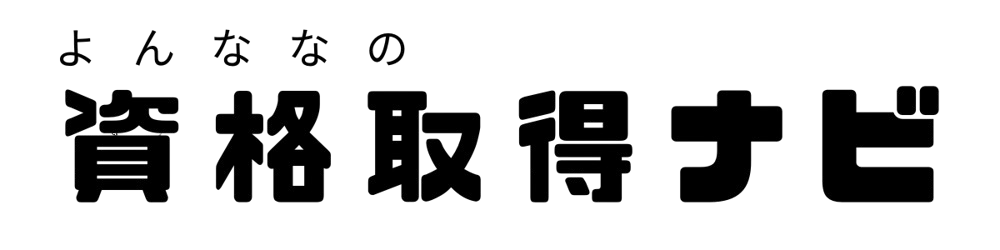
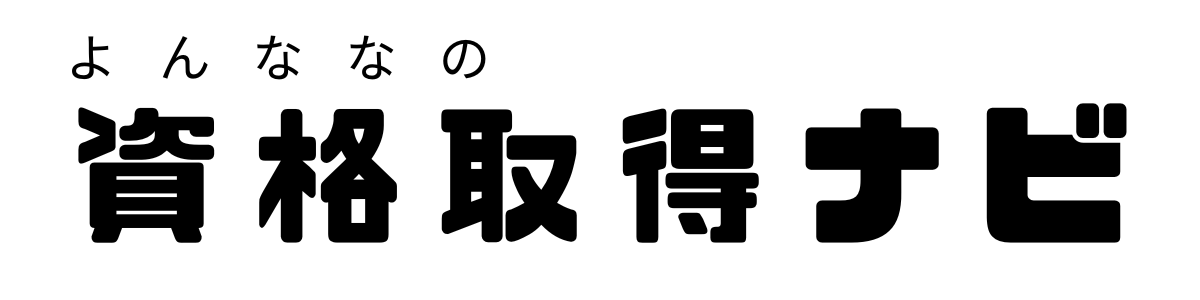
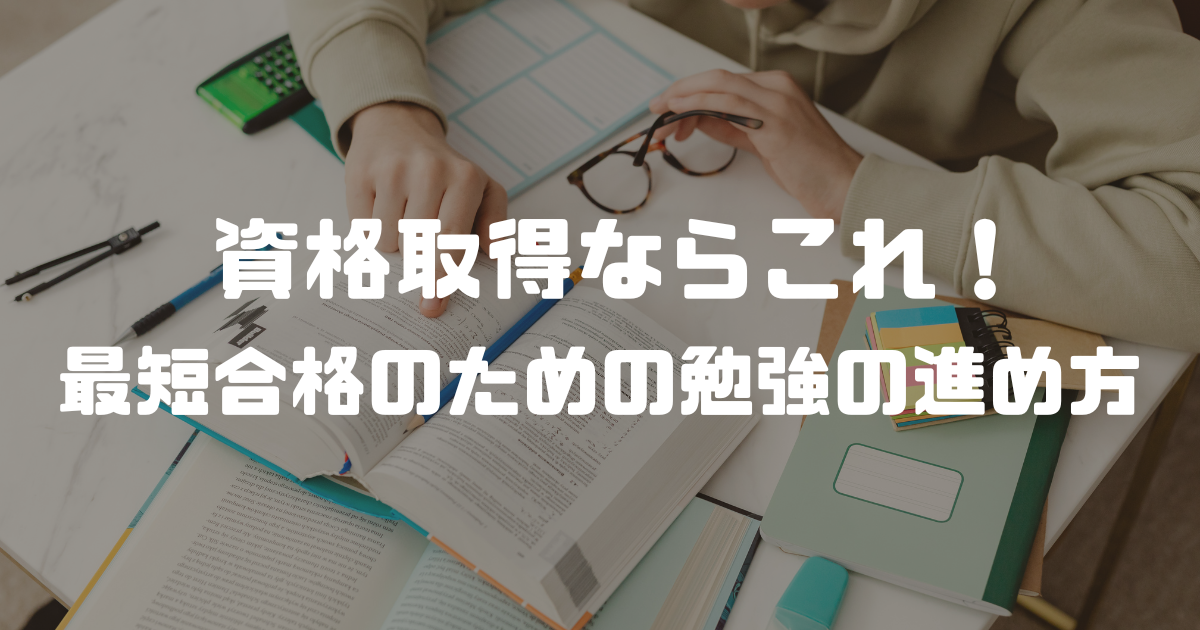


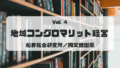
コメント