こんにちは。
よんななです。
1次試験を終えられた方は、おめでとうございます!
この記事はこれから2次試験の勉強を始める方、2次試験の勉強をしているけど躓いている方向けにお届けします。
今回は私が中小企業診断士2次試験に約50時間ほどの勉強で一発合格したコツと勉強法を、体験談ベースで徹底解説していきます。
結論から言いますと、「過去問を繰り返し解く」。これ以外に合格の道はないと考えています。試験内容を踏まえ、私が実践した勉強方法を徹底的に解説しますので、是非お読みください。
まだ中小企業診断士の試験未経験で、これから受験を目指す方、1次試験で科目免除を獲得されて来年目指される方も、「こういった試験内容がある」というのを知っておくだけでも今後の学習にプラスになると思いますので是非お読みください。
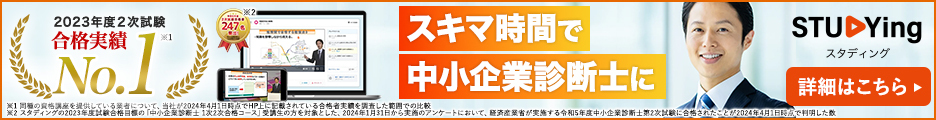
2次試験の日程
中小企業診断士2次試験(筆記)は、例年10月下旬の日曜日に実施されます。
2025年度 2次試験詳細
| 申込期間 | 2025年9月2日(金)~ 9月22日(月) |
|---|---|
| 筆記試験 | 2025年10月26日(日) |
| 合格発表(筆記) | 2026年1月14日(水) |
| 口述試験 | 2026年1月25日(日) |
| 合格発表(口述) | 2026年2月4日(水) |
| 受験料 | 17,800円 |
👉試験日は毎年微妙に変わります。
2次試験の科目
2次試験の筆記試験は「事例Ⅰ〜Ⅳ」の4つの記述式事例問題で構成されます。各事例80分で、1日で全4科目を解答します。事例ごとにテーマが異なり、以下のような内容です。
①組織・人事
②マーケティング
③生産・技術
④財務・会計
すべて記述式の問題となっており、時間との戦いになるため、単なる知識ではなく、論理的な文章構成と時間配分が重要になります。
また、意外と見落とされがちですが、二次試験は口述試験までがセットになっています。
筆記試験合格後に口述試験を受験し、口述試験の評定が60%以上の場合に合格を勝ち取ることができます。
2次試験の合格率
2次試験の合格率は、例年約18~20%前後で推移しています。1次試験を合格した猛者たちもここで不合格となる難易度の高い試験です。
なぜ、難易度が高いかというと、単なる知識問題ではなく、正確に出題意図を理解して、問われている内容に回答するということが求められるためです。
「試験なんだから当たり前じゃないの?」と思う方も多いかと思いますが、意外とこの単純なことができていないから不合格となるのです。
一般的な資格試験と比較すると合格率は低く、実力を問われる記述式試験の難しさが反映されています。問題の正解は公表されないため、自己採点が難しく、独学の人ほど戦略的な学習が求められます。
合格者の答案を分析したり、繰り返し過去問を解きながら、自分の課題を把握することが合格への近道です。
2次試験の合格基準
二次試験の筆記試験の合格基準は総得点が60%以上、かつ各科目で40%以上の得点を獲得することとなっております。
各科目はA,B,C,Dで評価され、Aが60%以上の得点を獲得しているという意味になります。
この得点(評価)は、得点開示請求というものを行わない限り、知ることはできません。得点開示請求は合格発表後に協会に依頼することで行うことができます。
1次試験と2次試験の関係/1次試験の高得点は意味がない?
1次試験の得点は、2次試験の合否に一切影響しません。仮に、1次試験ですべて100点をとっていたとしても、2次試験で優遇されることはありません。
また試験方法ですが、1次試験はマーク式なのに対して、2次試験は記述式であり、知識を問われる1次試験に対して、2次試験は設問の理解力と論理的思考力を試される試験となっています。
1次試験は他資格の取得状況や科目合格制度を利用した、科目免除がありましたが、2次試験には科目合格/免除制度はありません。
試験内容や求められる能力が異なるため、1次試験後すぐに2次試験の対策に切り替えることが大切です。
1次試験終了後に合格発表を待たずに早めに2次の過去問に取り組むことで、合格への戦略が立てやすくなります。
2次試験対策とおすすめの勉強法
1次試験対策の記事でも書きましたが、2次試験でも大切なのはやはり、アウトプットです。 教材や過去問を使いながらとにかくアウトプットしましょう。
2次試験は記述式問題なので、実際にペンを動かして繰り返しアウトプットしながら、教材や模範解答を見ながら悪かった点を確認して改善する。この繰り返しが何よりも大事です。
私が使った教材は、「ふぞろいな合格答案」(同友社)、30日完成! 事例IV合格点突破計算問題集(同友社)、そして自作のノート・再現答案です。
また、他の合格者の体験談から「中小企業診断士2次試験 事例IVの全知識&全ノウハウ(同友社)」もおすすめします。
2次試験は模範解答が公表されていないため、特に「ふぞろい」は必須のアイテムといえるでしょう。
「ふぞろい」は合格者、不合格者の解答事例をまとめ、それらのデータから合格、不合格の基準を分析して模範解答を導き出している参考書で、特に独学受験者は必ず購入することをおすすめします。
私自身も毎日過去問に取り組みながら、文章構成や要約力を鍛えました。繰り返し過去問を解くことで、出題意図や解答に盛り込むべき内容は何なのかをつかんでいきましょう。
100点をとる必要はないので、完璧な答案を目指すより、合格点を取れる解答作成力を意識するのがポイントです。
2次試験受験に際しての注意点
2次試験は知識・経験を問われる問題でないということを念頭に置いて受験しましょう。
もちろん1次試験で勉強した内容がすべて不要というわけではありませんが、予見文や設問に書かれていないことまで答えてしまうと試験としては間違いと判断されてしまいます。
具体的に以下の設問を例に開設します。
B社社長は、自社オンラインサイトのユーザーに対して、X島宿泊訪問ツアーを企画することにした。社長は、ツアー参加者には訪問を機にB社とX等のファンになってほしいと願っている。
絶景スポットや星空観賞などの観光以外で、どのようなプログラムを立案すべきか。100字以内で助言せよ。(令和2年事例Ⅱ 問4)
この問題はご自身の経験や知識からいろいろなアイディアが出てくるかと思いますが、問われているのは、「絶景スポットや星空鑑賞などの観光以外」で「ツアー参加者が訪問を機にB社とX島のファンになりそうなプログラム」を予見文を参考に解答するという問題です。
「絶景スポットや星空観賞」の内容を入れてしまうと当然間違いになりますし、予見文に書かれていないアイディアのような解答にならないよう気を付けましょう。
また「助言せよ」という設問なので、解答の締めくくりとしては「~につなげる」とか「~を図る」といった言葉で終わることが良いでしょう。
事例Ⅰの対策(組織・人事)
事例Ⅰでは、組織構造や人事施策に関する助言を求められます。
抽象的な課題が多いため、文章から情報を的確に抽出し、「問題→原因→対応策」という型で答える練習が必要です。
「権限委譲」「組織文化」「モチベーション向上」など頻出のキーワードは、事前に整理しておくと使いやすくなります。問題文と設問文をリンクさせて書く訓練がカギです。
事例Ⅰで覚えておいたほうが良いコツ
頻出キーワードは盛り込んで解答するようにしましょう。以前はたくさんキーワードを盛り込んだほうが良いという説もあったようですが、キーワード出現数で合格が決まるわけではないと考えられますので、キーワードを自然に盛り込み解答する程度がおすすめです。
中小企業診断士の受験者にはおなじみだと思いますが「茶化やサハホイヒ」という覚え方があります。茶化を分解するとサハホイヒというカタカナになっているので、どちらで覚えても大丈夫です。
サ:採用、ハ:配置、ホ:報酬、イ:育成、ヒ:評価 の頭文字となっており、人事戦略において重要なワードです。
その他、「サチノヒモケブカイネコ」という、サ:採用・配置、チ:賃金・報酬、ノ:能力開発、ヒ:評価、モ:モチベーション、ケ:権限移譲、ブ:部門設置、カイ:階層、ネ:ネットワーク、コ:コミュニケーションといった覚え方もありますので適宜使ってみてください。
こういった受験のコツも「ふぞろい」では会得することができます。
事例Ⅱの対策(マーケティング・流通)
事例Ⅱはマーケティングがテーマで、「誰に・何を・どう売るか」を念頭に置くことが大切です。
顧客ターゲット、商品特性、販売チャネルの整合性が問われるので、解答は一貫性が必須です。「地域密着」「リピーター獲得」「SNS活用」といった典型施策を覚えておき、設問ごとに当てはめる感覚を養いました。過去問分析を行い、過去に使われた施策や正答例からキーワードを抜き出してリスト化してみることをおすすめします。
事例Ⅱで覚えておいたほうが良いコツ
「Who(誰に)・What(何を)・How(どのように)」はマーケティングの基本ですので、この観点は忘れないようにしましょう。特にターゲット選定であるWho(誰に)の部分は、デモ・ジオ・サイコの観点で考えると考えやすいと思います。
デモグラフィック:性別、年齢、学歴、職業、所得
ジオグラフィック:地域、住居
サイコグラフィック:趣味・思考、価値観
また、他の事例でも共通していますが、中小企業診断士の試験では「問題」と「課題」を明確に区別しているので注意しましょう。
問題:●●の悪化、●●不足、●●が出来ていない、等
課題:●●の改善、●●不足からの脱却、●●のマニュアル化など
問題は、現状発生している悪いことやりそうとのギャップのことで、課題は問題を解決するために取り組むべきことです。
この「問題」と「課題」を意識せずに解答してしまうと不正解となります。
事例Ⅲの対策(生産・技術)
事例Ⅲでは中小製造業の現場課題が出題され、技術的な改善提案が求められます。「生産効率」「品質管理」「外注管理」など、現場の実態を想像しながら論理的に答える必要があります。図や表は出ないため、文章での説明力が重要です。改善前と改善後の流れを意識して書くと点が伸びやすくなります。理詰めの論述練習がカギとなります。
事例Ⅲで覚えておいたほうが良いコツ
事例Ⅲは、何と言ってもQCD(品質、コスト、デリバリー(納期))です。QCDの観点は必ず忘れないようにしましょう。
また、課題解決系のキーワードとしては、教育、研修、OJT、5Sなどがあります。
頻出キーワードについては、「ふぞろい」などでの紹介もありますが、自分自身で過去問を解きながらリストアップすることをおすすめします。
事例Ⅳの対策(財務・会計)
事例Ⅳは計算中心の事例で、損益分岐点、NPV、経営分析、CVP分析などが頻出します。計算問題については、二次試験科目の中で、唯一“答えがある”問題といってよいでしょう。答えがあるからこそしっかりと対策をすることで確実に得点を稼ぐことができます。
私は、とくに財務・会計が苦手だったので、計算練習を積み、苦手意識を払拭しました。
苦手な方は過去問だけでなく、問題集を購入し何度も解いて体に染み込ませていきましょう。
公式を覚えるだけでなく、問題文の読み取り力や計算のスピードが求められます。
暗算よりも電卓操作を重視し、本番と同じ環境で解くことが得点アップに直結しました。得点源にできれば大きな武器になります。
事例Ⅳで覚えておいたほうが良いコツ
事例Ⅳでは電卓の持ち込みが認められています。電卓の使い方をしっかり覚えておくと事例Ⅳの解答スピードが上がります。また、電卓は使い慣れたものを使いましょう。
メーカーによって「0」や「00」の位置や有無が異なっていたりもしますので、試験当日に焦らないよう、使い慣れた電卓で試験に臨むことをおすすめします。
H4:覚えると便利なMR機能
電卓にはMR(メモリーリコール)という機能があり、計算結果を覚えさせて、後で計算結果同士を合計することなどができます。
100 を入力し、M+ を押す。
200 を入力し、M+ を押す。
300 を入力し、M+ を押す。
MR を押すと、100 + 200 + 300 = 600 が表示されます
すでに知っているという方も少なくないかもしれませんが、私は中小企業診断士受験前まで単なる四則演算でしか電卓を使っていませんでした。この機能を覚えることでスピードが上がりましたのでぜひ使ってみてください。
二次試験全体を通じた、受験の心得3選
焦らない
試験当日になると、初見のワードが出てきたり設問が頭に入らず焦ることもあるかと思いますが、今までやってきたことを思い出して落ち着いて対応しましょう。
私は、事例Ⅰのコツでも記載した「サハホイヒ」のような頻出キーワードを試験開始と同時にメモ書きしておくことで、焦ったときにそこから使えるワードはないか、などを見て解答しました。
読める字で書く
試験時間が限られているので、きれいな字で書くことは難しいと思います。ですが、採点担当者が読める字で書くことは最低限必要です。
あきらめない
わからなくても最後まであきらめずに解答しましょう。試験後ほとんどの受験生が「落ちた」と思っているぐらい手ごたえを感じていません。ですが、意外なところで点数がついて、自信がなかった科目で「A評価」がついて合格した方もたくさんいます。私の場合は、事例Ⅳで計算が全く合わず、「不合格」を確信していましたが、計算過程の記載や、記述問題の部分をしっかりと書くことでギリギリ合格していました。どこが加点ポイントになるかわからないので、最後まであきらめず解答をしましょう。
勉強におすすめのツールや勉強道具
私が2次試験の勉強に使用した勉強道具をご紹介します。
1.ipad
Goodnote というアプリを使って学習しました。過去問をダウンロードしてノートに張り付けできるので、ダウンロードした過去問に直接書き込みながら、試験を解きました。
また、学習の途中で気づいた点や、注意したほうが良い観点などをノートにまとめていました。
2.Campasノート(コクヨ)方眼罫5㎜
実際の答案用紙よりも細かいですが、文字数のカウントがしやすいのでこちらを活用していました。ipadを使っても学習していたのですが、やはり紙のほうが書きやすかったり、実際の試験を想定しやすいので、ipadと実際のノートを併用していた形になります。
3.電卓
電卓はCASIOの「JF-120GT」という機種を使っていました。
ある程度の大きさがないと打ち間違えやすかったり、画面が見づらいのでこちらを選択しました。また、画面の角度を変えられるので試験会場でのライトの反射などを考えて調整できると考えるとこの電卓を選択してよかったと思います。
しっかりとMR機能もあるので、まだお気に入りの電卓がない方は是非ご参考にしてみてください。
2次試験の模試は受けたほうがよい?
模試は受けるべきだと思います。
私自身は独学で勉強していたため、模試というものがあることを知らずに本番を迎えましたが、独学で勉強しているとどうしても客観的な評価を得る機会がありません。
試験対策の方向性や感覚があっていれば問題ないかと思いますが、間違ったまま対策を続けていると全く点を取ることができない可能性もありますので、一度は受けてみることをおすすめします。
また、模試を通じて本番さながらの時間配分を体験できるほか、自分の弱点も明確になりますので受けたほうが良いと思います。
2次試験の持ち物/カラーペンは必要?
最後に、私の2次試験の持ち物をご紹介させていただきます。
シャープペンシル:私は筆圧が強く、すぐに芯が折れるので、3本持っていきました。
落としたり、芯が詰まるなど、何かあったときに対応できるよう複数持っていると安心です。また、小さい枠に文字を記載するため、私は0.3㎜のシャープペンシルをメインで使っていました。細い芯のほうが、小さい枠でもすっきりして採点者が読みやすくなると思います。
消しゴム:消しゴムも私は3個持っていき、2個を机に出していました。出しすぎると邪魔なので、必要最低限でよいと思います。
シャー芯:シャープペンシルの芯は忘れずに持っていきましょう。試験開始前に必ず確認して、各シャープペンシルには3‐4本の芯が入っている状態にしましょう。
カラーペン:カラーペンの必要性については意見が分かれるかと思います。私の場合は、対策時点ではカラーペンを使って色分けしていましたが当日は使いませんでした。理由は、カラーペンのキャップを開けたり閉めたり、色を選ぶ時間がもったいないからです。ルーティーンとして染みついている方は使っても良いかと思います。
電卓:事例Ⅳで必須のアイテムです。使い慣れたものを持っていきましょう。
※以前はメモ用紙として、答案用紙の最後のページを切り取る手法があったようですが、現在はページを切り取る行為は禁止されていますのでご注意ください。
まとめ
2次試験に一発合格するためには、「過去問演習」「合格答案の研究」「再現答案の作成」が非常に重要です。特にふぞろいシリーズは、独学者にとってのバイブルとも言える存在です。4つの事例にはそれぞれ特徴があるため、繰り返し過去問を解きながら「型を覚えてパターンに慣れる」ことが効率的な合格の近道です。焦らず地道に、自分の型を作り上げていきましょう。
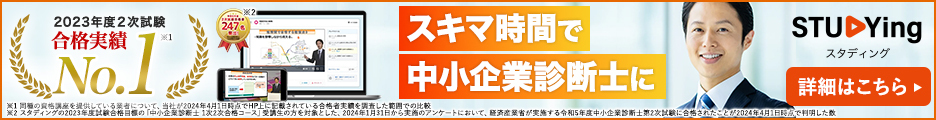
コロナ禍に会食の機会が減ったことをきっかけに独学で簿記2級に合格。そこから資格試験に目覚め、中小企業診断士、応用情報技術者、プロジェクトマネージャー試験に合格。難関資格合格の経験から最短合格を目指す方向けに資格受験のコツや勉強の進め方、通信講座の選び方をお伝えします。
現在は独立を目指しながら、企業内診断士として中小企業支援中
【保有資格】中小企業診断士、簿記2級、応用情報技術者、プロジェクトマネージャ試験など
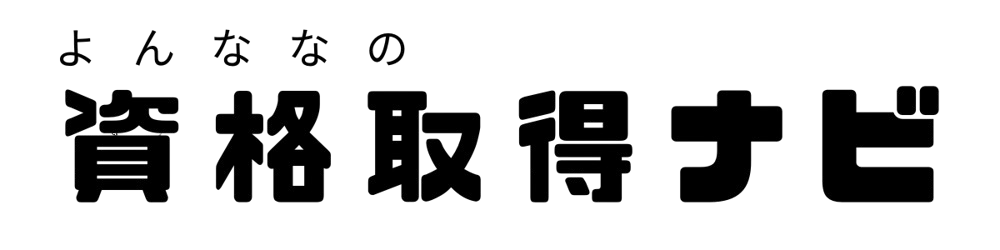
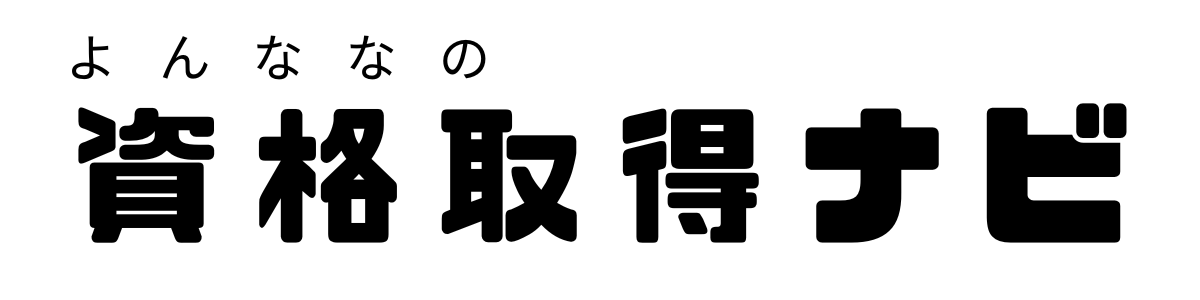
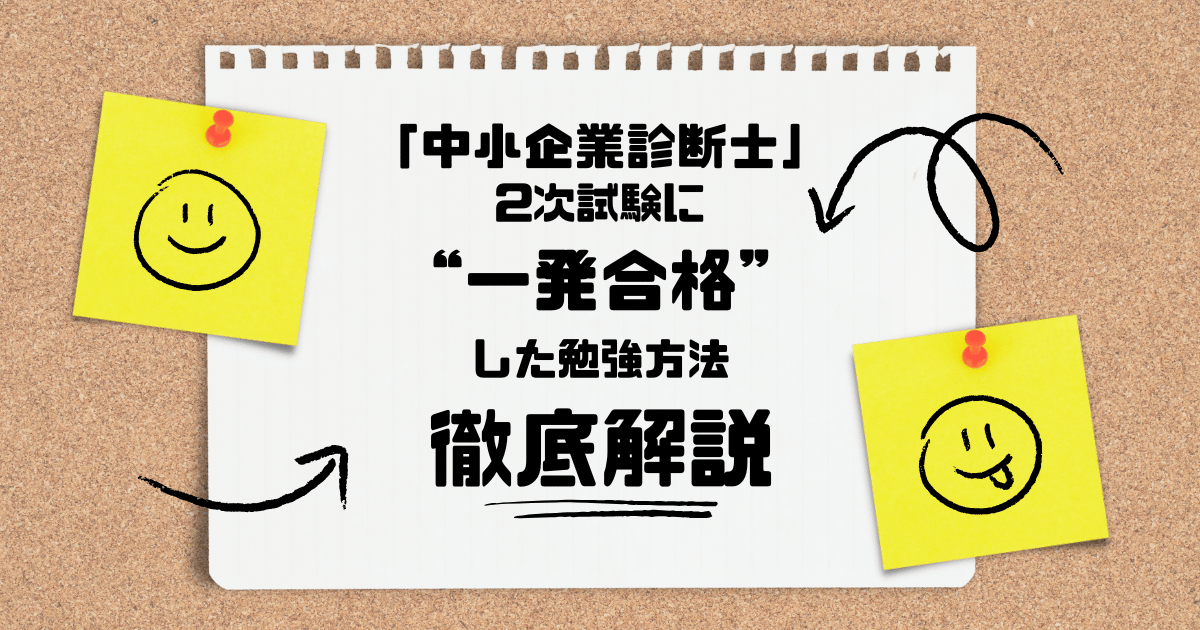

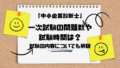
コメント